「日本のカロリーベース食料自給率は38%」
カロリーベース食料自給率という聞き慣れない言葉。カロリーベースとは、国内で消費される総カロリー量に対して、どれだけを国内生産でまかなえているかを示す指標です。日本はこのカロリーベースでわずか38%。つまり、食べているものの6割以上は海外に頼っているということです。例えば、買い物に行くと鶏肉は国産のものを多く目にしますね。国産と表示してある鶏が食べていたエサについて意識したことはありますか?日本で育った鶏でもエサの大半は外国産なのです。エサが外国産の場合、その鶏肉は国産としてカウントされないのです。日本は既に72%が外国産となっているという驚きの事実があります。
「食料自給率の低い日本」
カロリーベースで食料自給率は日本特有の指標ではありますが、食料安全保障の点から非常に重要です。他国のカロリーベース食料自給率がどうなっているか見てみると、主要8カ国の平均値(アメリカ・カナダ・ドイツ・フランス・イギリス・スイス・オーストラリア)が114%となっており日本の38%は群を抜いて低い水準にあるので驚きです。
| 国名 | カロリーベース食料自給率(%) |
| オーストラリア | 約233~309 |
| カナダ | 約204~233 |
| フランス | 約121~141 |
| アメリカ | 約104~132 |
| ドイツ | 約83~100 |
| イギリス | 約58~78 |
| スイス | 約60 |
| 日本 | 約38 |
「見落とされがちな輸入依存の話」
国産と表示されている鶏肉でも多くは海外から輸入されたエサを食べて育った鶏です。農林水産省のデータによると、国産のエサでのみで育った鶏肉は8%程度(令和元年度)と鶏肉全体の1割にも満たないのです。鶏肉は健康志向の高まりから国内の需要は高まっていますが安価な輸入品も増加しているのです。
「減少したお米の消費量“日本人はなにを食べているの”」
昭和の時代に1人1年あたり100キロを超えていた日本人のお米の消費量は令和になり50キロまで減りました。その分日本人は何を食べているのでしょうか。小麦でしょうか。小麦の消費量は増加していますがお米の減少した分を賄うほど増加していません。増えたのは揚げた畜産物、つまり唐揚げ、トンカツ、チキンナゲットなどを食べているのです。鶏肉などの畜産物の消費量が高まっているということはその分輸入されるエサの量も増加していることになります。エサの主成分はトウモロコシです。日本人は多くの穀物を消費していることになります。日本人の食は輸入によって成り立ってということは驚きです。
「コメ消滅」という本のタイトルは大げさである、怖いなどのイメージを持たれるかもしれません。しかし日本の食について考えるきっかけを与えてくれました。
次回は“パンの材料ってどこから?”をテーマに、小麦と私たちの暮らしを見ていきます

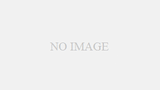
コメント