
「日本のスーパーからコメが消えた」
“令和の米騒動”は2024年から始まり、まだ続いています。今年になりわたしも実感することになりました。テレビでも“お米が足りない”、“値段が上がっている”とニュースになっていましたね。日本人の主食でとても大事なお米が、当たり前に手に入ることに慣れてしまい買えなくなるなんて思いもしませんでした。農家さんが作ってくれたお米が食べられることは当たり前ではないのだと感じました。
「減反政策ってなに」
日本ではたくさんのお米が作られてきました。でもパンなどを食べることが増えてお米が余るようになりました。そこで政府は1970年ごろに
“お米を作らないこと”に対して支援してきたのです。その支援が長きました。2018年に国が農家さんにお米の作る量を示すことはなくなりました。でも補助金(お米ではなく麦や大豆などの他の作物を作ると補助金が出る)が続いていたので減反政策は実際に続いているという声もあるのです。
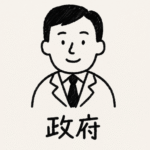
「これ以上お米が余らないように、お米を作る面積を減らしてほしい」
と農家さんにお願いをし、作る量を制限するようになりました。これが“減反政策”と呼ばれているのです。そしてこんなことを農家さんに伝えました。
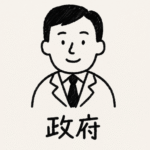
「お米を作るのをやめて他の作物(麦や大豆など)を作ってくれたら補助金を出しますよ」
このように“お米を作らないこと”に対して支援してきたのです。そしてその支援が長く続きました。2018年に国が農家さんにお米の作る量を示すことはなくなりました。でも補助金(お米ではなく麦や大豆などの他の作物を作ると補助金が出る)が続いていたので減反政策は実際に続いているという声もあるのです。
「農家の高齢化と担い手不足の現状」
家族のなかで一番農作業をしている人は6割が70歳を超えていてます。29歳以下の人は1%しかいないのです。そのために日本は農業が若い世代に伝えられずに衰えていくのではないかと不安に思われています。このままではお米が作られる量はどんどん減ってしまいます。今は外国の方も日本でたくさん働いています。もし外国の方が日本の農業を学んだとしても、いつまで日本で働くのかはわかりません。農業を日本で守るには、日本のわたしたち自身が受け継いでいくことが大切なのだと感じました。
お米不足を通して現在農業に携わっている方がとても貴重な方々であると実感しました。
わたしは農業の知識も経験もありません。それでも何かできることがあるのではないか。そう思うようになりました。
次回は、「わたしたちにできることってなんだろう?」をテーマに考えてみたいと思います。
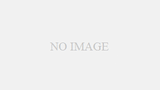

コメント