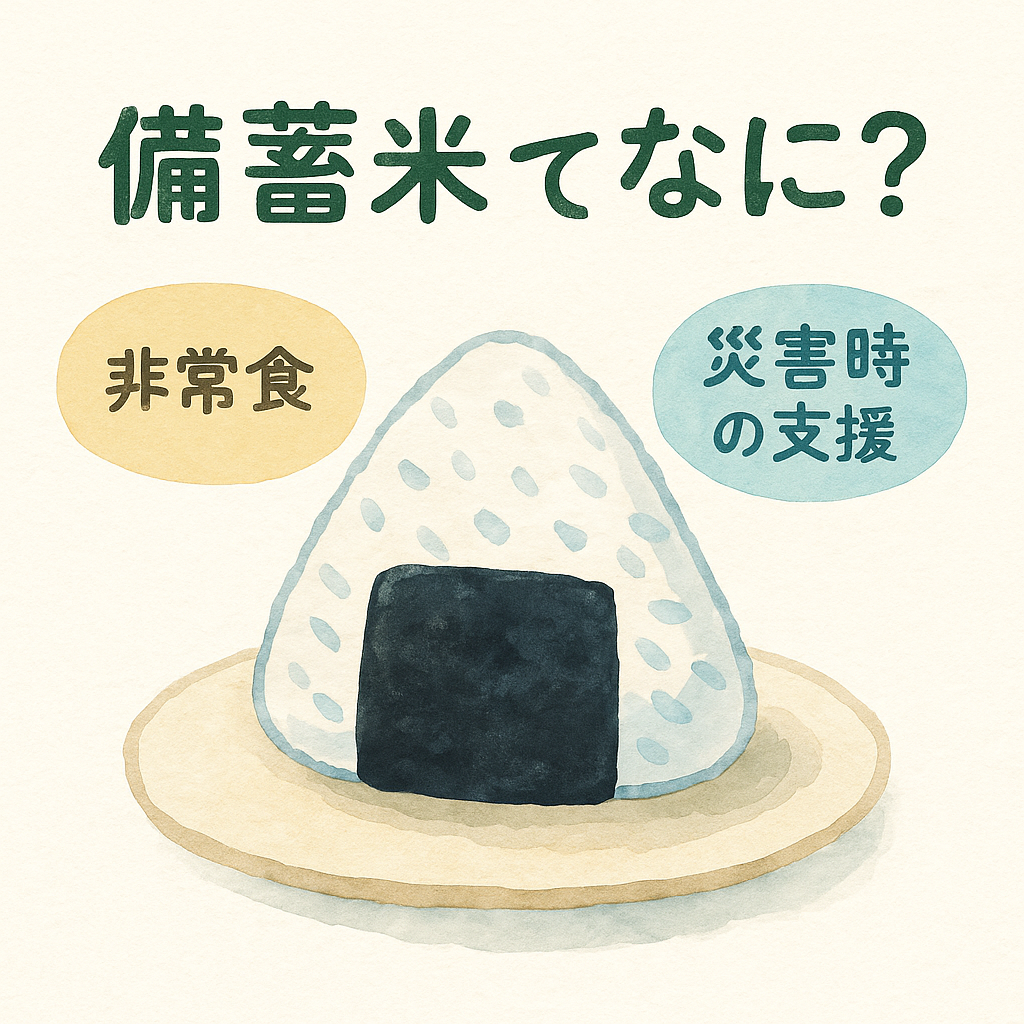
「備蓄米てなに?」
災害のときやお米が収穫できないときなどの“いざという時”に備えて保管されているお米のことです。災害のときだけでなく発展途上国などへの支援にも使用されることがあります。昔はお米を年貢として納められていましたが、今は違います。現代の備蓄米は、国が必要な量を“買い取って”保管しているのです。
「備えるお米」
日本は備蓄米をおよそ100万トン維持できるようにしています。100万トンは10年に1度の不足や2年連続の不作にも対応できる量となっています。買い入れたお米は5年間保管されます。古くなったものから飼料用などとして買い取られ、また新しいお米と入れ替えられます。
「命をつなぐお米」
地震や台風などの災害が発生したときに避難所や被災地域へ無償で提供されます。また道路が寸断されて通ることができなくなったときに、自衛隊や支援団体が備蓄米を炊き出しに使用されていて、備蓄米は“命をつなぐお米”となります。
これまで備蓄米が使用された実例
・阪神・淡路大震災(1995)
・東日本大震災(2011)
・熊本地震(2016)
・能登半島地震(2024)
このように備蓄米は“いざという時”に備えてあるお米なのです。
食の安心を支える“見えないインフラ”のような存在となっています。

次回の記事はお米が食卓に届くまでです。


コメント