
「本当に赤字なの?」
お米農家さんの95%は10ヘクタール未満でお米を作っています。小さな規模で作っている農家さんがほとんどなのです。そして規模が小さい農家さんは売上よりも経費が高くなってしまい赤字となっている現状があります。
*1ヘクタール:10000平方メートルで東京ドームのおよそ1/5の広さです。
現在規模が小さい農家さんが国内で作られるお米の半分を担っています。
実際にはお米農家さんが別に収入があったり、補助金や直接販売をして得られた収入があったりするとプラスとなる場合もあるのです。
「お米農家さんを支えるしくみ」
①経済的な支援
山間地域での条件が厳しい土地で頑張る農家さんへ支給。
災害が起きたときの補償制度
麦や大豆、エサとなる飼料用米へ切り替えることで交付金を支給。
②技術や知識の支援
JAなどが農作物への病気や害虫対策をアドバイス
ドローンやAIの導入を助ける支援
③販売に対する支援
地産地消の推進:道の駅や地元の学校給食で地元のお米を使ってもらうようにする取り組み
輸出支援:高級ブランド米など海外へ日本米を輸出することを支援
6次産業化支援:農家さんが自分で加工・販売ができるように支援 甘酒や米粉パンなど
④後継者・新規就農者への支援
若い人が農業を始めるときに無利子で資金を提供、就農前・就農初期に給付金が支給される制度
⑤環境・地域への支援
地域で田んぼのあぜ道や水路を守る活動をしているグループに支援金を給付
農薬や化学肥料を減らす取り組みに対して助成される制度

様々な支援がありますが、これは“高齢化が進み、農家さんの後継ぎが少ない”ことが問題となっているからです。そしてお米の消費量が減っているので収入も下がっているのです。また天候不順や資材高騰の影響で利益が出にくいのです。
お米づくりは水や自然・文化を守る役割も担っているのですね。
「飼料用米とはなに?」
飼料用米とは牛・豚・鶏などのエサにするために作られるお米のことです。
飼料用米へと切り替えて安定して収入を得ることができる場合も多いのです。
収穫後のコストが抑えられるメリットもあります。
でも注意点もあります。
〇食用米から切り替える手続きが大変
〇農家さんの技術力やブランドは評価されない
という点があります。
農家さんは
・ブランド米を育てる
・飼料用米や加工用米などで補助金を活用する
・複数の田んぼで食用米と飼料用米の両方を育てる
という方法を組み合わせて収入のバランスをとっているのです。
お米を作るだけで安定した収入と生活を得ることは難しいことが分かりますね。
「それでも農家さんが続ける理由」
多くの農家さんが「日本の文化を守る」、「田んぼがあることで水害を防ぐ」「地域の景観・自然環境を保つ役割がある」という思いをもって、大変ななかでもお米づくりを続けているのです。
わたし自身日本の農業の現状を知るなかで、お米農家さんに対する感謝の気持ちが増してより地元でとれたお米や野菜、国産のものを買いたいと思うようになりました。
次回はお米がどのように販売されているのかです。

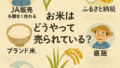
コメント